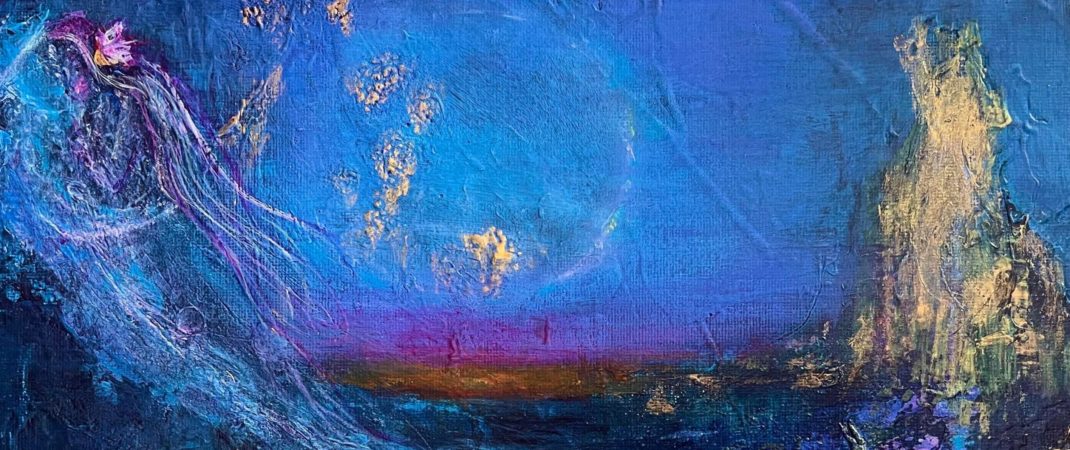1. Alalá de Muxía / Trad.
高野陽子(Vo.),Sally Lunn(Psalterium),Tomo Yoshikawa(Hurdy Gurdy)
私が魂の故郷と感じるほどガリシアで一番魅かれた海沿いの美しい海の街、Muxía ムシアに伝わる歌。サンティアゴ巡礼の聖地でもあり、コルーニャ県のこの辺りの大西洋に面した約150kmの海岸は、Costa de Morte (死の海岸)と呼ばれている。
この地の伝説によると、聖サンティアゴ(ヤコブ)が布教活動がうまくゆかず失意の底にあった時、海の向こうから天使に導かれた小舟に乗った聖母マリアが現れ、悩めるサンティアゴを励ましたという。
聖母は「船の聖母 Nosa Seiora da Barca」として海からすぐの岩の上の礼拝堂に祀られており、すぐ近くには聖母が乗ってきたという船の帆と伝わる「揺れる岩」があり、この歌の歌詞にも登場している。巡礼者たちは自分の悩みが聖母に聞き届けてもらえたかどうかを、この岩に乗って占う。揺らすことが出来れが聞き入れてもらえ、巡礼の目的が達成されたこととなる。
もう一つ聖母が乗ってきた船の船体とされる「腰の岩」は、地面と岩の隙間を這って9回くぐると 腰痛が治ると信仰されている。「9」という数字はガリシアの民間信仰に根付く数字で、私も訪れたことのあるサン・アンドレス・デ・テイシドという巡礼の聖地にも、「9つの波」の力を身体に受けて3人の乙女が身を清めるという伝説がある。
「3」という数字は私も大好きなケルティック文様のひとつである「トリスケル」に象徴されるように、ケルト世界では祈祷的な意味をもつ数字。聖なる数字「3」を三回繰り返す(=「9」)によって、その力がより強まり、厄を浄化すると考えられてきたそうだ。
聖サンティアゴ(聖ヤコブ)のお墓が発見されるローマ・カトリックの流れの以前からケルトの修道士達が海を渡って石の船で航海していたという伝説がガリシアだけでなく、アイルランドやブルターニュなどのケルト文化圏の各地に伝わっている。
この歌からも、伝説、物語の古層にはケルト、そしてもっと古代の民間信仰などが、時のミルフィーユのように折り重なっていると感じる。
海の彼方にある「常世の国」「異界」「死者の世界」…舟は「あの世」と「この世」を結ぶ乗り物だ。
この歌の背景には波の音を入れたいイメージがあり、いくつかの自分で録音した波音からエンジニアさんに採用されたのは 日本の聖地のひとつでもある熊野の海、那智の浜での夜の海の波音。
熊野にも海の彼方に理想郷・常世の国の伝説があると信じられており、僧侶たちが浄土を目指して捨て身で船で海を渡っていった補陀落渡海の出発点でもある。
曲のエンディングでこの波音をバックに聴こえてくる鐘のような響きも、中世古楽奏者のSally Lunnさんによるプサルテリウム演奏。伝統的なイギリスの教会の鐘のルールに「Plain Hunt on six Bells」 という奏法だそうだ。そして海を渡るカモメの鳴き声も、数年間のガリシア音楽留学から帰国されたTomo Yoshikawaさんによるハーディ・ガーディ演奏。
中世の楽器やハーディ・ガーディの特性について私は勉強不足で、かなり制約が多いことを打合せの段階で知ったのだが、自分の中では 依頼するのはこちらのお二人による組み合わせで1曲目に配置するというプランは最初から明確に持ち合わせていた。
2. Camariñas / Trad.
高野陽子(Vo.) hatao (Low Whistle, Tin Whistle, オカリナ) 上原奈未:(Celtic Harp)
上沼健二(さざ波ドラム, Percussion)
ムシアと同じくCosta de Morte (死の海岸)沿いの小さな港町、カマリニーャス。ムシアからもバスが出ている。美しいレース編みの工芸品が盛んな地域。
主人公はカマリーニャスの女の子に恋をしていた。しかし彼はカマリニャスの出身ではなく、今は離ればばれになり、悲しみの世界にいる。「あなたはもう僕をカマリニャス人にしている」という歌詞から推測すると、移民の歌かもしれない。
ガリシアを代表するグループ、Luar na Lubreや スコットランドのヘブリディーズ諸島出身のゲール語歌手、Julie Fowlis などもとりあげげている。
3. Ondas do mar de Vigo / Martín Codax
4. Quantas sabedes amar amigo / Martín Codax
高野陽子(Vo&Cho) Sally Lunn:(Psalterium,Percussion) Tomo Yoshikawa(Hurdy Gurdy)
13世紀のガリシアの三大吟遊詩人のひとり、Vigo(ビーゴ)出身のマルティン・コダックスの作品「カンティガス・デ・アミーゴ Cantigas de amigo 」より2曲を取り上げた。これは、アルフォンソ10世 によって編纂された聖母マリアの奇跡を称えたカンティガ集、「Cantigas de Santa Maria(聖母マリア頌歌集) 」とは異なり、世俗の愛を謡った当時の流行歌ともいえる。
行方のわからないまま なかなか帰ってこない愛しい人を ビーゴの海でひとり待つ女性が 波に語りかける 孤独な愛の歌。今回の【ガリシアの孤愁】という邦題は、この曲からのインスピレーションに最も影響を受けている。
今作のガリシア語や朗読で大変お世話になった、日本におけるガリシア語の第一人者、浅香武和氏編著の「吟遊詩人マルティン・コダックスー7つのカンティーガス」より翻訳を一部、抜粋させて頂く。
【Ondas do mar de Vigo】ビーゴの海の波よ あなたは我が愛する人にお会いになりましたか ああ デウス様、彼の人はすぐに戻るでしょうか
【Quantas sabedas amae amigo】いくばくか愛する人を 慈しむことができましょうか ビーゴの海に私とおいでください そして波間で戯れましょう
5. Cantiga da Montaña / Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre
高野陽子(Vo. 三線 Cho.) hatao:(篠笛, Tin Whistle), 上原奈未(Celtic Harp)上沼健二(Percussion, Cho.)
敬愛するガリシア伝統音楽歌手&Pandeireta/パンデイレタ(タンバリン)奏者である Xabier Díaz (シャビエル・ディアス)& Adufeiras de Salitre のアルバム ‘’The Tambourine Man’’の収録曲。シャビエル氏の現地でのパンデイレタのワークショップにも参加し、コンサートも数えくれないくらい程、たくさん赴いた。車が運転できない私は電車やバスを乗り継ぎ、一日かけてガリシアの山奥の会場へ向かうこともあった。
Cantiga da Montañaとは、山の歌 という意味。好きな人に想いを伝えられない’サウダージ≒モリ―ニャ(Morriña)が曲のテーマともいえる。この曲も移民の伝統歌かもしれない。
Xabier Díaz氏 の公式You Tu beより。本家のCantiga da Montaña
6. Alalá das Mariñas / Trad.
高野陽子(Vo.&Cho.) 小嶋佑樹 (gaita/Galician Bagpipe) 上原奈未(Celtic Harp)
ガリシアのルーゴ在住の歌手から初めて教わった伝承歌で、ガリシアではとても有名な伝承歌。歌詞の真意は、あくまで私の推測だが、主人公はこの世の住人でなく、天界から眺めているような気がする。その眼差しの向こうは、長年住んでいたなつかしい白い家、月桂樹やオレンジの木が生い茂る庭、そして愛していた人への想いに溢れている。
ガリシアのケルト音楽祭、オルテゲイラでも優勝の経歴を持つ小嶋佑樹 氏の奏でる、ガイタ(ガリシア地方のバグパイプ)の伸びやかな音色が、上原奈未さんのやさしいハープの響きと相まって天空を駆け巡るイメージ。
7. Xota de Pazos de Borbén / Trad
高野陽子(Vo. Pandeireta/パンデイレタ)